調査研究資料の役割
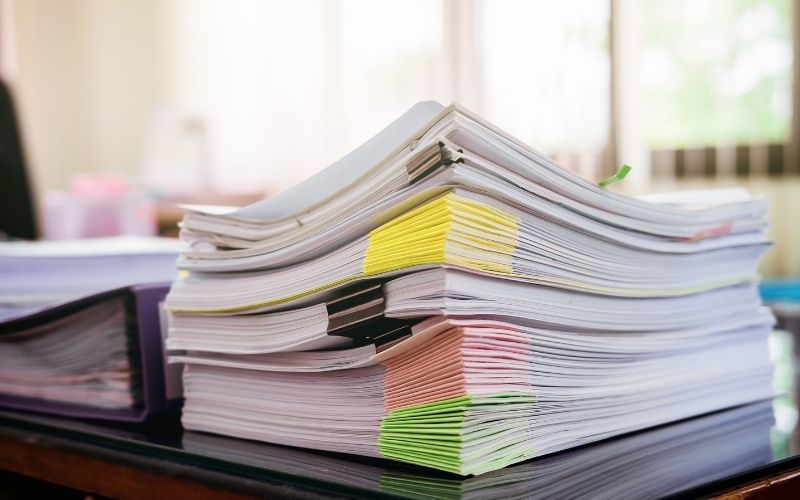
※本記事は、「F-wave」(2024年6月号)に掲載されたコラム(なぜなにNPO vol.179)を引用・再編集したものです。
ボランティアについての資料を整理した中に、2007年に文部書科学省が調査した研究資料「諸外国におけるボランティア活動に関する調査研究報告書」を見つけた。
調査研究のための実行委員会を組織し、発表したものであるが、その目的には「今後の施策の推進の基礎資料に資する」とある。
諸外国とは、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、スウェーデン、韓国、中国の7か国である。
調査項目は、ボランティアに関する考え方、社会的背景、制度、施策、制度外の活動、活動のための社会的基盤など諸外国の実情に合わせ、多岐にわたっている。
改めて読み進めると、あることに気付いた。
調査後、教育基本法の改正が行われていた。その教育基本法の改正では、前文に書き加えられた言葉がある。
【我々は、この理想を実現するため、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。ここに、我々は、日本国憲法の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する。】
これを受けて、第2条(教育の目的)の条文にも【教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い 、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。四 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと】が加えられ、改めて生涯学習の理念が第三条【国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。】として新設された。
前文にボランティアの精神である「公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備え」が入り、「教育」の概念の中に「学習」という言葉が入ってきたことは当時衝撃的だったことを思い出した。
この調査がどれほど「施策の推進の基礎資料に資する」という目的を達成したのかはわからないが、諸外国のボランティアの調査が実施されたことは、事実だと思うとボランティア活動の底力を感じる。
そして時期を同じくして、民法の改正を伴う公益法人制度改革も行われ、非営利法人の社会的価値が大きく動いた。
法の改正後、社団法人・財団法人の認識は変わり、2022年には労働者協同組合法も制定された。
省庁を超えて参考資料となったのかどうかはいささか判断に迷うが、当時の動きを改めて確認し、今後の動きに着目したい。
