日本ボランティア・NPO・市民活動年表
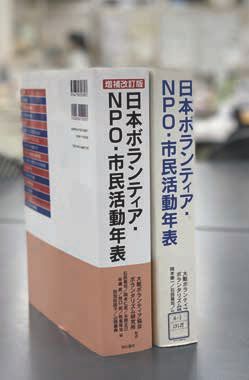
※本記事は、「F-wave」(2022年11月号)に掲載されたコラム(なぜなにNPO vol.160)を引用・再編集したものです。
「日本ボランティア・NPO・市民活動年表」の改訂内容
大阪ボランティア協会ボランタリズム研究所の「日本ボランティア・NPO・市民活動年表」の増補改訂版が届きました。ページ総数1,100p、5.5cmの超大作です。
2014年初版から8年が経ち「ボランティア・NPO・市民活動」業界の動きは目まぐるしく、増えた分野は「ジェンダー」「地域づくり」「復興支援」、「反戦」の言葉は「平和」ともに年表が作成され、「支援組織」と「支援行政」は、別の分野となりました。
これだけでも、社会の動きを反映している感があります。
初版を読みだしてから、市民の自主的な活動の江戸時代末期からの動きをつぶさに知ることができ、納得のできる事象や現代の活動のルーツなど、読むたびに今でも新しい発見があります。
時代区分は、大きく3つに分けてあり、
・創生期(明治維新~第2次世界大戦終結まで)
・成長期(第2次世界大戦終結~NPO法成立まで、増補版ではバブル崩壊まで)
・発展期(増補版では展開期)(NPO法成立以後、増補版ではバブル崩壊~現代まで)
としています。
特に、創世記からは、歴史の教科書にもなかった事象が数多く記載されており、先人の多様な運動や活動が持つ、民衆の生活に根付いた深い歴史と思想によって紡がれていることを学びました。
長く続いた町民互助社会であった、江戸時代の幕引き前夜から明治・大正・昭和と続く市民活動等創世期の動きは、現代の市民活動等のある意味幕開けだったのではないかと思います。
増補版を手に取り、「はじめに」をまず読みました。「市民による多様な運動や活動は民衆の生活に根付いた深い歴史と思想を持っている」という文章が目に留まりました。
続いて「本書には、現在よりはるかに困難な状況の中で持続的に困難に立ち向かい、現在の市民活動の権利を勝ち取った人々の経験やそこからくる知恵が、豊かに息づいている。戦前においても、人々は決して単なる『臣民』として受動的に権力に従い忍従してきたのではなく、ともに手を取り合って歴史を作り上げてきた。」とあり、「市民活動の年表は、市民によって作られて続けていくべきであって、その作業には読者の参加が必要である」ともあります。
これからの年表に新しい動きを創り出すのは、今動いている皆様なのです。
市民活動推進センターの図書コーナーには、初版と増補改訂版があります。
ぜひ手に取って興味のある所だけでも読んでみませんか。今後の活動のヒントが見つかるかもしれません。
藤沢市でNPOに関するご相談なら……
藤沢市内のNPOや市民活動団体、ボランティア団体で困りごとやお悩みがありましたら、ぜひ市民活動支援施設までご相談ください!
